出典研究の第一人者による頻出問題の宝庫
いよいよ大御所の登場だ。原仙作『英文標準問題精講』(略して「原仙の英標」)といえば、1933(昭和8)年の初版以来、英文解釈分野では受験生のアイドル(?)的参考書だった。(写真左は1954年版、右は1982年版)

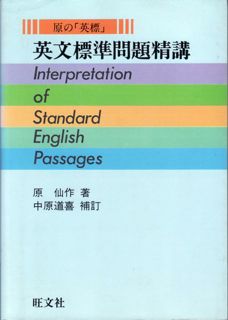
『週刊朝日』1971(昭和46)年3月5日号によれば、この時点で最もよく売れている参考書ベスト5に「原仙の英標」が入っていた。
1位 赤尾好夫編『英語基本単語熟語集』(豆単)旺文社、1942初版、700万部
2位 小野圭次郎著『英文の解釈』山海堂→小野圭出版、1921初版、520万部
3位 星野華水著『チャート式数学I』研数出版、1927初版、300万部
3位 山崎貞著『新々英文解釈研究』研究社、1912年初版、300万部
5位 原仙作著『英文標準問題精講』旺文社、1933年初版、260万部
2位 小野圭次郎著『英文の解釈』山海堂→小野圭出版、1921初版、520万部
3位 星野華水著『チャート式数学I』研数出版、1927初版、300万部
3位 山崎貞著『新々英文解釈研究』研究社、1912年初版、300万部
5位 原仙作著『英文標準問題精講』旺文社、1933年初版、260万部
では、なぜ売れたか?
何よりも、入試問題の出典と出題傾向を明示してあるからだった。
受験生にしてみれば、勉強の的が絞りやすいのである。
巻頭の「問題出典表」には著者と作品名と問題番号が明記されている(以下は1954年版)。
何よりも、入試問題の出典と出題傾向を明示してあるからだった。
受験生にしてみれば、勉強の的が絞りやすいのである。
巻頭の「問題出典表」には著者と作品名と問題番号が明記されている(以下は1954年版)。

こうして原は「出典研究の第一人者」とか「英語入試問題研究の第一人者」という異名を取ることになる。
原によれば、「明治の末葉より大正の初期にかけては、試験問題の種本といへば反射的に〔John Lubbockの〕Use of Life が想起された」という。
拙著『日本人は英語をどう学んできたか』(研究社、2008、pp.78-79)より、『英標』の各版から調査した出典を年代順に並べてみよう。各時代に、どんな英文が好まれたかが一目瞭然となる。
拙著『日本人は英語をどう学んできたか』(研究社、2008、pp.78-79)より、『英標』の各版から調査した出典を年代順に並べてみよう。各時代に、どんな英文が好まれたかが一目瞭然となる。
特に1962年版からはRussell, Maugham, Huxleyらのエッセイ風の作品が圧倒的な人気を誇るようになる。戦後の平和と民主主義、科学技術の時代にふさわしい作家たちである。

表のすべての時期を累積すると、昭和期の入試に出た作家ベスト10は次のようになる。
Hearn(小泉八雲)が堂々の歴代1位。西洋化一辺倒の時期を経て、昭和期には古き良き日本の面影を求める気分が広がっていたのかもしれない。

こうした頻出の「おいしい」問題群が、威圧感のないコンパクトな本の中に効率よく収められている。
全4編で、1日5問ずつ解けば、40日間で終わる設定になっているのだ。
受験生が焦り出すのが秋だとして、10月から始めても1月には「完成」するわけだ。

注解は親切で、訳も分かりやすい。
なにより、複雑な文構造を「解剖」することで骨格を示し(この手法は明治期からあった)、「なんだ、単なるS+V+Cだったんだ!」と思わせるところがすごい。
これが後の時代には「細かすぎる」と批判されることになるのだが・・・。

『英標』の出典を見ると、明治・大正・昭和の40年代頃まで、文学的な香りのする散文が高校生に読まれ、入試に出た英文の王道だったことがわかる。
そこから、若者は「いかに生きるべきか」「何をなすべきか」を、ときに苦悶しながら、真剣に考えた。
それらの作品群がほとんど読まれなくなってしまったとしたら、若者たちは何を土台にして自身の生き方を模索するのだろうか。
それらの作品群がほとんど読まれなくなってしまったとしたら、若者たちは何を土台にして自身の生き方を模索するのだろうか。
ケータイが片ときも手放せない「あ・かるい」我が娘を見て、オヤジは今日も苦悶の日々を送っている。